最近フードテックという言葉を聞いたりするけど具体的にどんなトレンドが出てきてるのかな?食品業界で働いてみたいし気になる。
食べることって身近だから今後どう変わっていくのか気になる…
食と人の関わりって奥が深そうだけど食の未来ってなんだか不安…子どもにも正しい知識で食育したいしな。
 ユウイチロウ
ユウイチロウ僕は2012年から9年ほど食品メーカーで研究や開発をしてきました。最近、関心のあったフードテック革命という本を読み食のトレンドが大きく変わるんだと衝撃を受けました。
 ユウイチロウ
ユウイチロウ今回は最新のフードテックについて具体的なトレンドを過去、現在、未来の切り口で学べる「食べることの進化史」について解説します。
✔本記事の内容
- 「食べることの進化史」の目次・概要
- 「食べることの進化史」を読むべき人3選
- 「食べることの進化史」の注目ポイント
それではぜひ最後までお読みください。
「食べることの進化史」の目次・概要

「食べることの進化史」の目次
- 序章 食から未来を考えるわけ
- 第1章 「未来の料理」はどうなるかー料理の進化論ー
- 第2章 「未来の身体」はどうなるかー食と身体の進化論ー
- 第3章 「未来の心」はどうなるかー食と心の進化論ー
- 第4章 「未来の環境」はどうなるかー食と環境の進化論
※参考文献リスト付き
著者の石川伸一氏は東北大学農学研究科を修了後、宮城大学で分子調理学を専門とした先生をされています。
本書では食の未来を語る上で料理、食と身体、心、環境のについて、現在・過去・未来の切り口で分かりやすく解説されていて食のトレンドを歴史ベースで学ぶことができました。
ちなみに石川さんの研究室Webサイトはオシャレで洗練されていて、食×テクノロジーについて詳しい方なんだなと思ったり。さらにTwitterも定期的に更新されているようですね。
ページ数
ページ数は全312ページでごく一般的な文庫本と同じ程度です。
さらに参考文献リストも掲載されており食に関する根拠も掲載されているので勉強になりますね。
「食べることの進化史」を読むべき人3選
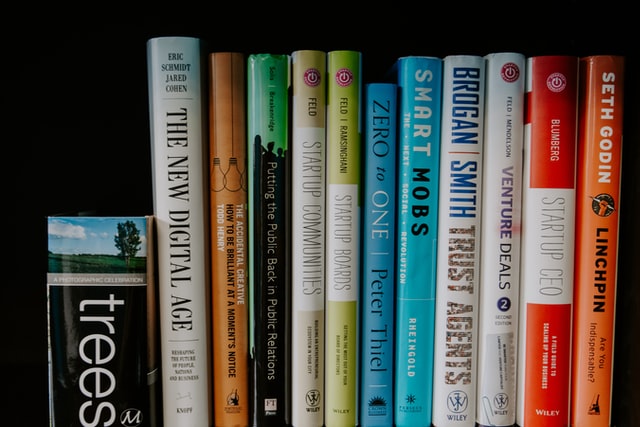
食品メーカーを志望している就活生・大学生
将来、食品メーカーで商品開発をしたい!って方は必読の本かなと思います。
理由は食トレンドを過去・現在・未来の切り口で学ぶことができ将来自分のやってみたいことのヒントが得られるからです。2020年は新型コロナウイルス騒ぎで世界が一気に変わりましたよね。
もちろん食の世界も大きな変化が予想され、より人々が食に美味しさだけでない価値を求めだしています。そんな食トレンドの変化を学びつつ将来やってみたいことのヒントにしてみてはいかがでしょうか。
食品業界で仕事している社会人
僕も食品業界で仕事している人間ですが必読の本かと感じました。フードテック革命もかなり刺激になる本でしたが、本書は過去・現在・未来の切り口で歴史をベースに記述されているのでより未来を考える上で勉強になります。
著者はサピエンス全史の農業革命にも触れているので、歴史的観点で食べることの歴史を深堀りしつつ今後どのように変化していくかまとめたのでしょう。


食に関心にある主婦・子育中のママやパパ
お子様がいる方も食や料理に興味・関心があるのではないでしょうか?
食の正しい知識はネット上で探すのは結構難しいので、参考文献が掲載されている本には信頼性がありますよね。
食育という言葉があるように食べることは生涯に渡って営むことなので子どもに正しい知識を伝えるために本書は大きな助けになるでしょう。
「食べることの進化史」の注目ポイント3つ

過去・現在・未来の切り口で食トレンドの変化が理解しやすい
「食べることの進化史」は歴史ベースの話から現在を認識しつつ未来を語っているので理解しやすいと感じました。
歴史を学びつつ新しい知見を吸収できるので理解しやすいですよね。
例えば、第2章「未来の身体」はどうなるかー食と身体の進化論ーでは以下のような切り口で書かれています。
【過去】食と人類の進化物語
- 食による祖先の自然選択
- 肉に魅せれられた人類
- 大きな脳を可能にしたもの
【現在】食と健康と病気
- 食べることと健康の因果関係
- 肥満の進化生物学
- 食欲の制御と暴走
【未来】食と身体の進化の未来図
- 健康になるためのテクノロジー
- ヒトは未来食によってどう進化するのか
- 脱進化するヒト、脱人間化するヒト
まずは人類が何を食べて生き延びていきたか、実は原始霊長類は昆虫を主に食べつつフルーツや若葉などを食べていたようです。その後は果実離れが起こり芋なども食べてましたが、変化が大きかったのが肉でした。
みなさんも肉は好きですよね?
人類は歴史的にも肉に魅せられて狩猟採集によって、植物性食品だけでなく狩猟によって肉を食べるようになりました。
私達の祖先はずっと他の動物のそばを素通りしていたわけですが、「食べもの」としてみなすようになったのはナッツがきっかけでした。
ナッツは脂肪分が豊富でナッツを食べることで油脂の味を覚え、脂質の消化に関わる小腸が発達したんですね。
肉を食べ始めたきっかけは気候変動が起こり、食料を見つけるのが難しくなったからと考えられています。肉から栄養をとることの効率性が大きく、ウシ科の動物ステーキは同じ量のニンジンを食べた時の5倍のエネルギーが得られ、必須タンパク質や脂肪も摂れるんですね。
しかし現在はエネルギーや脂肪の摂りすぎで肥満などの健康問題が起こっています。
日本では感じにくいですが、肥満は世界では大きな健康問題のひとつです。世界人口の3人に1人が肥満または過体重となっているようです。この現状から肥満はすでに「パンデミック(世界的大流行)」状態と考える研究者もいます。
最大の要因は食にあり、肥満の要因仮説として、①節約遺伝子仮説、②料理仮説の2つがあるようです。
①は食料が乏しい環境を生き抜くため、飢餓に適応した遺伝子で効率的に脂肪などを溜め込む体質が仇になっているという仮説。
②は生食と比較して、消化吸収率の高い調理された料理を食べるようになったことがヒトを太りやすくしたのではないかという仮説。
どちらも現代ではジレンマに感じる部分もありますが遺伝子はすぐに変えられないし、料理しないと全てを生食はできないし難しいですよね。
一方、未来では健康になるためのテクノロジーとして個別化食が進むという予想です。
みなさんは自分にあった食を求めるときはどんなことを考えますか?
例えば、健康になりたい、特別食(アレルギー・嚥下、減塩対応の食)を食べたい、食で共感したいみたいなことを考えないでしょうか。
最近は個人の健康状態をアプリやデバイスを使ってデータにすることが簡単になりましたよね。
今後はデータ化がどんどん進み、例えば健康診断の結果や個人の現在の体重、食べたものの種類と量によってデバイスが食生活改善のアドバイスをくれたりすることが当たり前になってくるかもしれません。
以上、「食べることの進化史」では過去、現在、未来と時制で食べることの変化を理解することができます。
豊富な参考文献リスト
「食べることの進化史」では過去、現在、未来を語る上で必要になった参考文献リストが巻末に書かれています。
根拠資料があることで自分も学び直しができたり、情報の信頼性が上がりますよね。
「食べることの進化史」は読むだけじゃなく、さらに自分が興味を持ったテーマについて深堀りする上でも役立つ本かな感じました。
情報量が多いがページ数はフツウ
目次の通り食トレンドの変化についてかなり詳細に書かれていますがページ数は300ページほどで普通に読めるボリュームでした。
また、自分が知りたい所だけ読むのもありで僕は食が身体に及ぼす影響を一番知りたかったので第2章をしっかり読みました。参考文献も気になったのを読めたので満足です。
こんな感じで自分が知りたい所を深堀りして読むのもありですね。
今回は以上となります。
